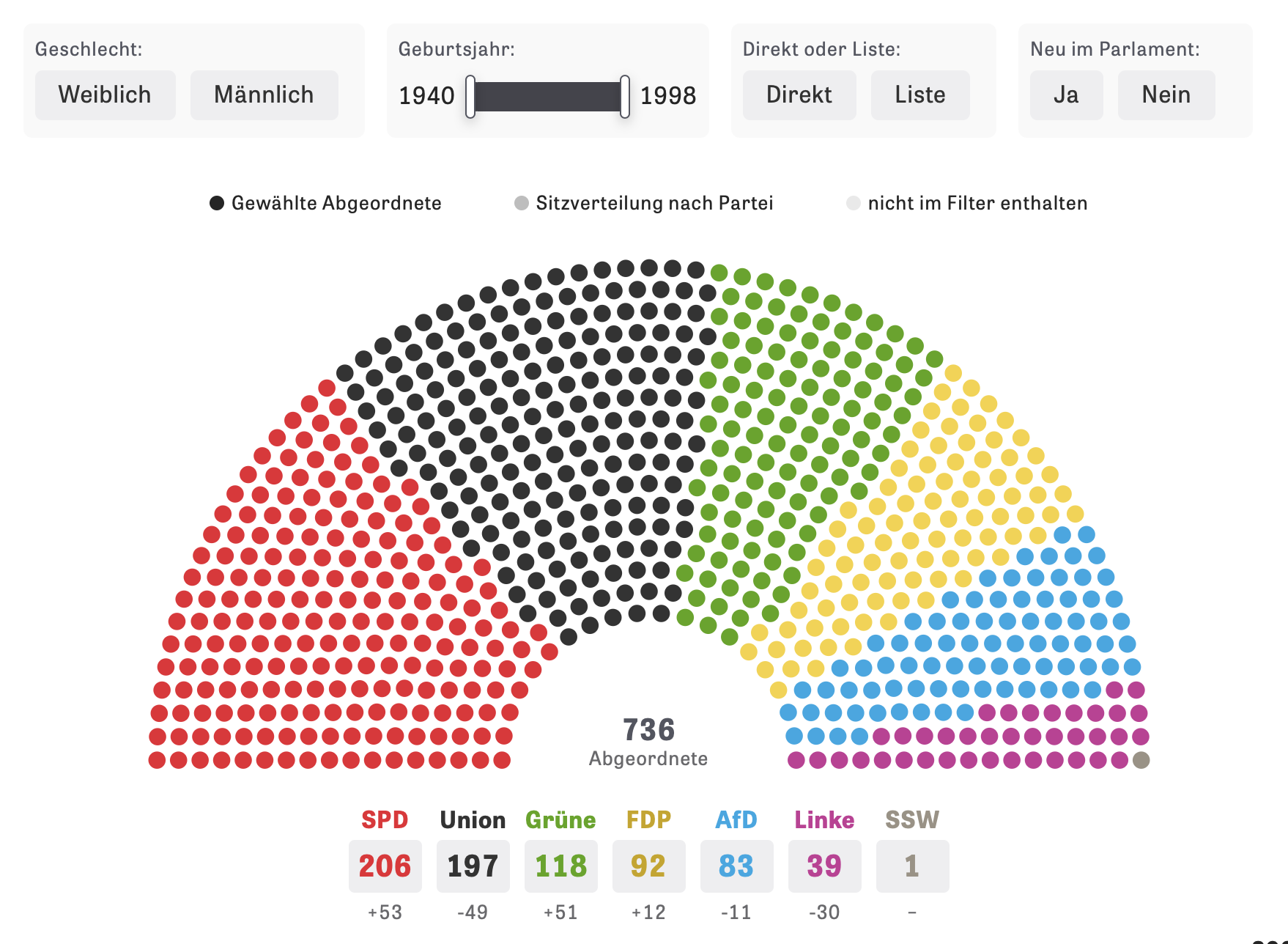ポン・ジュノ or ホン・サンス? – ポン・ジュノ and ホン・サンス! 『ドライブ・マイ・カー』&『偶然と想像』
ナンニ・モレッティの『親愛なる日記』にとても好きな場面がある。それは三部構成の第一部「ベスパに乗って」の一場面で、モレッティが交差点で信号待ちをしていると隣にオープンカーがやってきて停車する。この車とそれを運転している男を見たモレッティは、不意にベスパから降りて男に近づき、一方的… Read More »ポン・ジュノ or ホン・サンス? – ポン・ジュノ and ホン・サンス! 『ドライブ・マイ・カー』&『偶然と想像』