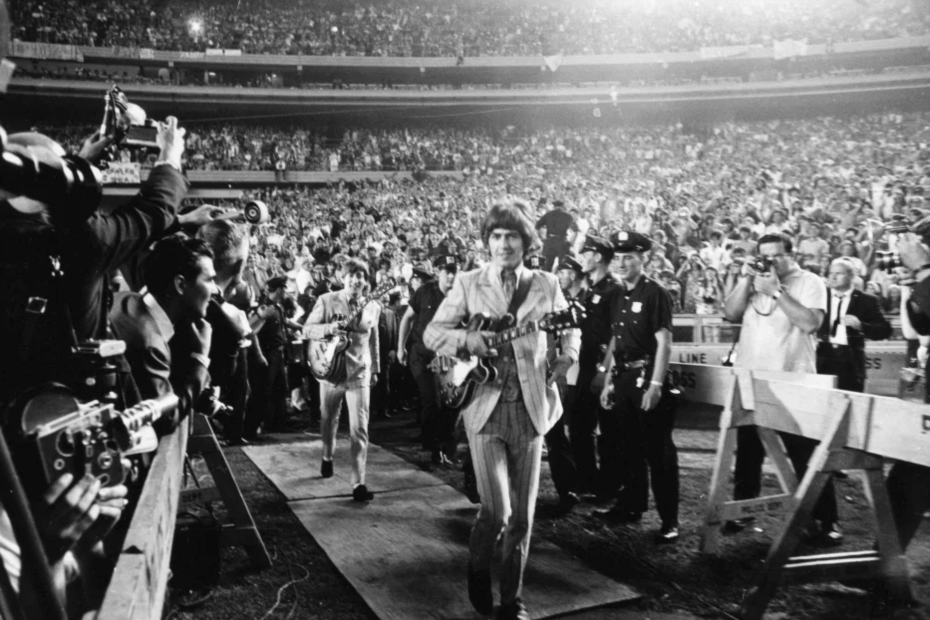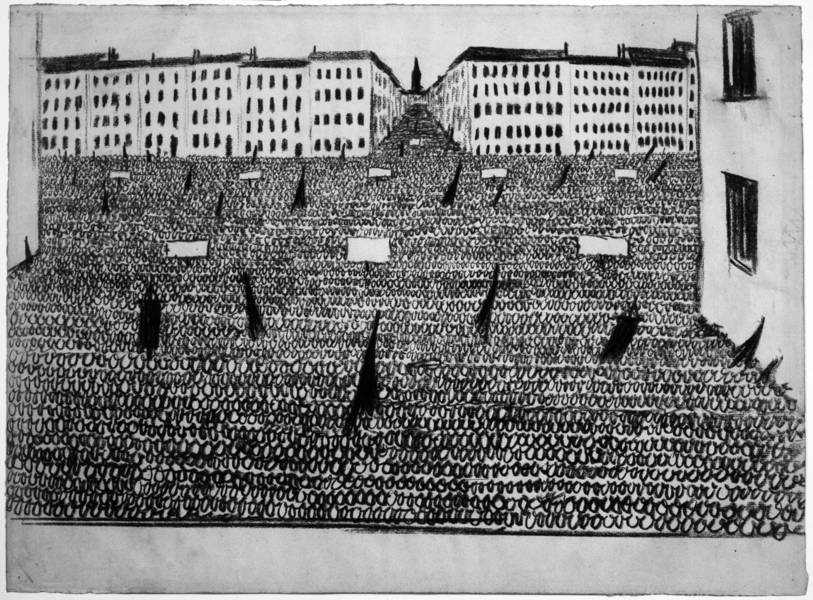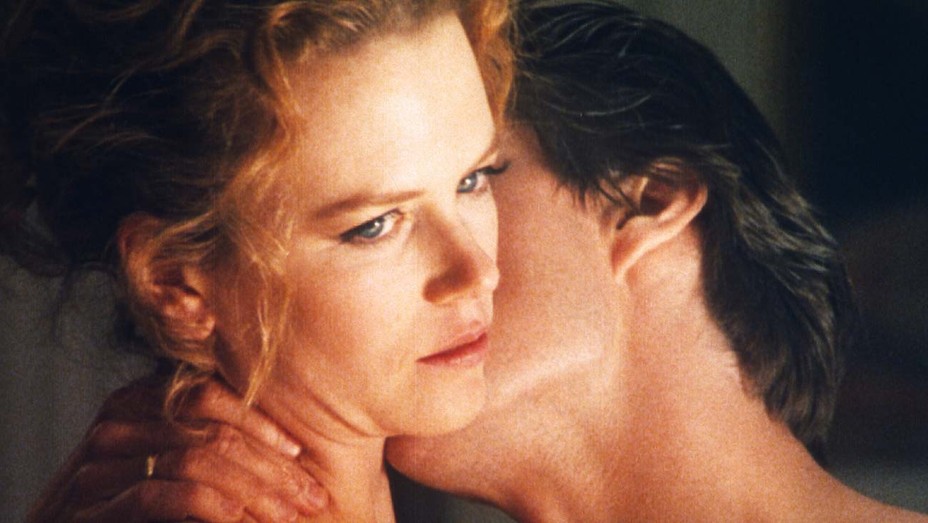メディア技術に媒介された文化におけるライヴ・パフォーマンス(フィリップ・オースランダー)
授業用教材として翻訳したフィリップ・オースランダーの文章を公開します。 Philip Auslander: Liveness. Performance in A Mediatized Culture (Second Edition, 2008) の第2章 “Live performance in a mediatized culture” の部分訳です。オースランダーの著作は複製技術メディアとライヴ的なものの関係を議論するさいの基本文献として、いまなお重要性を失っていないと思います。今回はオースランダーによるライヴ性(Liveness)概念の再検討の中核をなす部分を取り出して訳出しています。