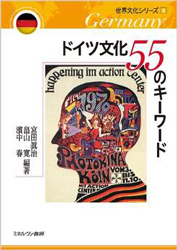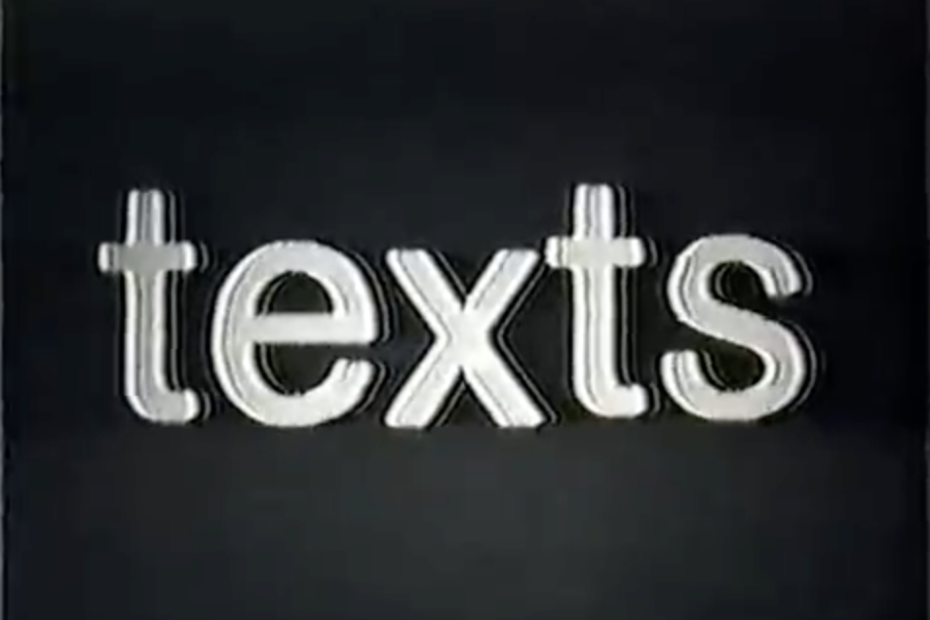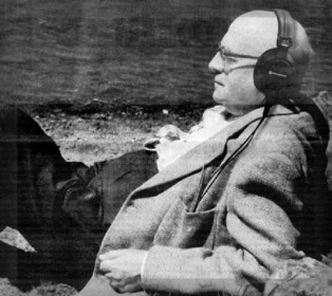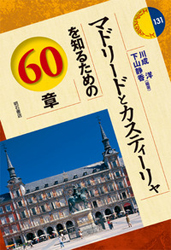〈映画都市〉としてのマドリード アルモドバルの初期作品における都市表象をめぐって
本論文では、スペインの映画作家ペドロ・アルモドバルの二本の初期作品に描かれる都市の表象を「映画都市」(cinematic city)の観点から考察しています。
「映画都市」とは、映画における都市表象の研究において、特に2000 年以降盛んに議論されるようになった概念ですが、映画と都市との多面的な結びつきを考えるにあたって有益な観点を提出しています。
この論文ではまずアルモドバルとマドリードの関係を概観した後に、映画都市の概念を検討し、それをアルモドバルの初期作品に登場する都市の表象の分析に援用することによって、それらの作品に見られる映画と都市経験の結びつきを具体的に考察することを試みています。『表現文化』第9号所収、36-67頁、2015年。