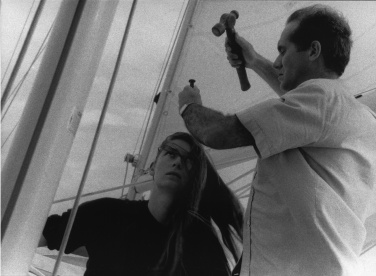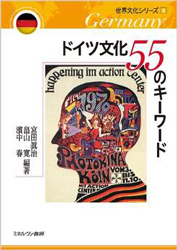映画川 『大和(カリフォルニア)』
boidマガジンに映画評を寄稿しました。今回は宮崎大祐監督の『大和(カリフォルニア)』について書いています。本作は2018年4月7日より、新宿のK’s cinema を皮切りに全国6都市の映画館で順次公開されることになっています。米軍厚木基地の立地である大和市を舞台にしたこの作品は、日本とアメリカの関係を主題にした作品としてだけでなく、今日の地方都市の匿名的で貧しい風景と映画がいかに向き合うのかという点でも、ヒップホップの思想と音楽性を物語の中枢に導入する試みとしても、非常に野心的な作品になっています。